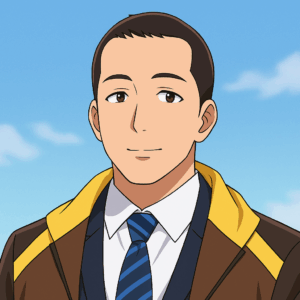運送会社ではないけど安全管理者の選任は必要なの?怠ると罰則もあります!

目次
1・安全運転管理者の選任が必要となる企業
安全運転管理者は、「乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車を5台以上使用している事業所(自動車使用の本拠地)」ごとに選任する必要があります。なお、自動二輪車1台は0.5台として計算し、50cc以下の原動機付自転車は含みません。
2・副安全運転管理者が必要となるケース
使用する自動車の台数が20台以上になった場合、20台以上40台未満は1人、以下20台ごとに1人ずつ安全運転管理者を補助する者として副安全運転管理者の選任が必要です。
副安全運転管理者の業務内容は、基本的に安全運転管理者の業務と同じです。
副安全運転管理者の選任には、副安全運転点管理者として経験を積むことで次の安全運転管理者を育てるという意図も含まれます。
3・安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者の選任は、次の資格要件を満たす人を任命しなくてはなりません。
- 年齢が20歳以上(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)
- 運転管理の実務経験が2年以上
- 過去2年以内に安全運転管理者の解任命令を受けていないこと
- 過去2年以内に、ひき逃げや酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、妨害運転など、一定の違反行為をしていない、および下命・容認をしていないこと
4・安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者および副安全運転管理者は、安全運転促進と事故予防・削減を目的に、主に次の業務を行います。
(1) 運転者の状況把握
車両を運転するドライバーの適正や運転技能、知識、道路交通法などの規定遵守を把握するための措置を講じます。
(2)安全運転確保のための運行計画作成
ドライバーが安心安全に業務を遂行できるように、過労運転を防止しつつ、業務を調整し、適切な休憩が取れるように運行計画を作成します。
(3)長距離、夜間運転時の交替要員の配置
長距離および夜間運転を行わせる場合、疲労や睡眠不足で安全な運転ができなくなる恐れがあるため、交替するドライバーを配置します。
(4)異常気象時等の安全確保の措置
異常気象や天災などにより、安全な運転が確保できない恐れがあるとき、状況に応じて適切な指示出しを行います。
(5)点呼等による安全運転の指示
ドライバーに対して運転前に点呼を行い、日常点検の実施状況と車両に関する注意事項や報告事項の聞き取り、病気や疲労によって運転できない可能性を確認し、安全な運転を確保するための指示出しを行います。
(6)運転日誌の備え付けと記録の管理
ドライバーが使用する車両に運転日誌を備え付け、ドライバーの情報、運転開始と終了時刻、走行距離、業務内容など、その日に必要な情報を記録します。管理者は日誌を確認し、ドライバーの管理を行います。
(7)運転者に対する安全運転指導
交通安全教育方針にもとづき、ドライバーへ運転技能や遵守すべき交通ルールなどの知識を教育します。
(8)酒気帯びの有無確認に関する記録と保存
1日2回、運転前後にドライバーの酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録します。
記録したアルコールチェック記録簿は1年間保存して管理します。
(9)アルコールチェッカー(アルコール検知器)の使用等
アルコールチェッカーを用いて酒気帯びの有無を正確に測定します。また、アルコールチェッカーは毎日確実に測定できるよう、故障がないかを確認したり、メンテナンスをしたりするなどして有効な状態を維持します。アルコールチェッカーによっては、使用期限がありますので、期限切れがないかをよく確認して下さい。
※またアルコールチェッカーについては、複数の人間が使用することから衛生上、除菌をすることがありうると思います。しかし、息を吹きかける周辺(検知部分)をアルコール成分を含むもので除菌をしてしまうとその後の点呼時においてアルコールを検知してしまいますので、注意しましょう。
5・各種届出の義務
安全運転管理者と副安全運転管理者を選任したら、「15日以内」に自動車の使用の本拠を管轄する警察署を経由し、公安委員会に届け出ることが義務付けられています。
また、事業規模が縮小し自動車の台数が基準以下になったときや、事業所が移転・閉鎖したとき、あるいは人事異動や退職などに伴い、安全運転管理者等を改任・解任・変更した場合も、同様の日程で届出を行わねばなりません。
6・法定講習の受講義務
安全運転管理者と副安全運転管理者は、年に一度、公安委員会が行っている法定講習を受講しなくてはなりません。管轄公安委員会から講習受講を促す通知と講習申出書が送付されますので、その内容に従い、毎年一回、受講するようにしましょう。
なお、同講習の代理受講は認められておらず、必ず選任された本人が受講しなくてはなりません。途中退席禁止ですが、月に5~6回程度、さまざまな会場で随時開催されているため、日程調整をして受講しましょう。
7・安全運転管理者制度に関する4つの違反と罰則
安全運転管理者制度に関して、下記の違反行為が見受けられた場合、次のような罰則が科せられます。-
- 安全運転管理者を選任しなかった場合「選任義務違反」
対象であるにも関わらず安全運転管理者を未選任だった場合、50万円以下の罰金が科せられます。 - 安全運転管理者を解任しなかった場合「解任命令違反」
安全運転管理者に対する公安委員会からの解任命令に従わず職務を続行した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 - 是正措置命令が出ても従わなかった場合「是正措置命令違反」
安全な運転が確保されていないと認められ是正措置を命じられたにも関わらず適切な対応をとらなかった場合、50万円以下の罰金が科せられることになります。 - 安全運転管理者等の選任届と解任届を提出しなかった場合「選任解任届出義務違反」
適切に届出が提出されなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
8・まとめ
国の経済発展に伴い、自動車は産業・経済・文化の発展に大きく寄与し、今やなくてはならない交通手段の1つとなっている反面、交通事故による人の死傷や排ガスなどの交通公害といった社会問題をもたらし、そのような状況の中、誕生したのが「安全運転管理者制度」です。
また法改正のきっかけとなった出来事として、2021年6月28日、千葉県八街市で発生した痛ましい交通死亡事故が起きてしまいました。これまで、安全運転管理者は運転前に正常な運転ができるかどうかを確認することは義務つけられておりました。
しかし、運転後においては酒気帯びの有無を確認すること、またその確認内容を記録することは義務つけられておらず、確認方法すら具体的に定められておりませんでした。
この事故を受けて、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者の行うべき業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等を新たに設けることとなったのです。
コンプライアンスを重視している企業様であれば、しっかりと安全運転管理者を選任していると思われますが、中には、
「うちは運送会社ではないから大丈夫。」「面倒くさいから届出は後回しにしよう。」
といった企業様があるのも事実です。
余談にはなりますが、警視庁ホームページでは、
安全運転管理者選任事業所一覧
というものを公表しておりますので、第三者からも容易に確認できてしまいます。
届出は、自動車の使用の本拠地を管轄する警察署へすることとなっており、オンラインでの申請も可能ですが、管理者証の受領及び返納、変更で事業所を管轄する警察署へ行くこととなります。
平日に時間を取って、警察署へ行くのが面倒、悪い事はしていないが警察署自体が苦手であるという方がいれば、当事務所では安全管理者選任届出提出代行を11,000円より行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
いまだに痛ましい交通事故は発生し続けていますので、従業員の安全はもとより、一般市民を巻き込む事故を起こさないといった気概をもって、企業の義務として取り組んでいきましょう。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・国分寺市・国立市・武蔵村山市・昭島市・瑞穂町・福生市・立川市・府中市・日野市・羽村市・あきる野市・青梅市・練馬区・杉並区の◆運送業の新規許可◆貨物軽自動車運送事業届出(黒ナンバーでの運送)◆事業報告書・実績報告書の作成、提出代行◆第一種貨物利用運送事業登録◆自動車運転代行業◆レンタカー事業許可(自家用自動車有償貸渡許可申請)◆貨物軽自動車安全管理者の選任・届出はHAYABUSA行政書士事務所まで!