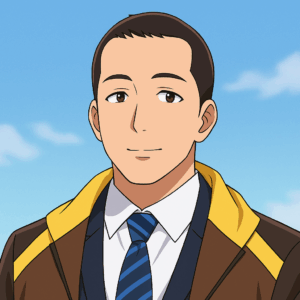遺言書の「検認(けんにん)」とは?
検認とは簡単に説明すると「家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらうこと」です。
1・ 検認の目的
- 遺言書が確かに存在していたことを確認する
- 遺言書の形状や日付、内容、署名の有無などを記録する
- 遺言書の改ざん・隠蔽・偽造防止
※ 検認は「遺言の有効性を判断する手続き」ではなく、形式的な確認になりますので、遺言書の有効・無効を判断するものではないので注意して下さい。
2・検認が必要なケース
- 自筆証書遺言(本人が手書きで作成)
- 秘密証書遺言(署名捺印して封印されたもの)
※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、検認は不要です。
3・検認が不要なケース
- 公正証書遺言の場合は、公証人が関与しているため、検認を経ずにすぐに執行可能となります。
4・ 検認の手続きの流れ
(1)相続人調査・必要書類の収集
・申立書
・遺言書原本
・遺言者の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
(2)家庭裁判所に検認の申立て
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出して、検認の申し立てます。
検認を申し立てる人は、通常、
・遺言書を保管していた人
・遺言書を発見した相続人
等です。
(3)家庭裁判所からの検認期日の通知
申立てがあると相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が行われます。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは行われます。
※申立人は、遺言書・印鑑・その他担当者から指示されたものを持参します。
(4)検認
・検認期日には、申立人から遺言書を提出してもらい、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が遺言書を検認します。
※封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。)
・検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となりますので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)をすることになりますので覚えておきましょう。
5・期間と注意点
・検認の申立てから検認期日までには1〜2か月程度かかることがあります。
・検認を受けずに遺言書を開封したり、勝手に執行すると5万円以下の過料の対象になる場合があります。
※検認前に開封してしまったからといって無効になることはないので、そこは安心して下さい。
6・ポイントとして
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 自筆証書遺言・秘密証書遺言 ※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、対象外 |
| 手続き先 | 家庭裁判所(遺言者の最後の住所地) |
| 必要性 | 改ざん防止のため必須(公正証書遺言及び自筆証書遺言書保管制度利用時は不要) |
| 実行可能時期 | 検認後に遺言の内容が執行できる |
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査・成年後見業務)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!