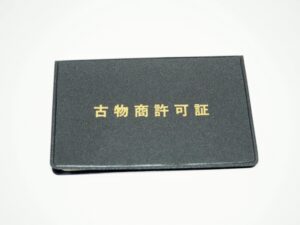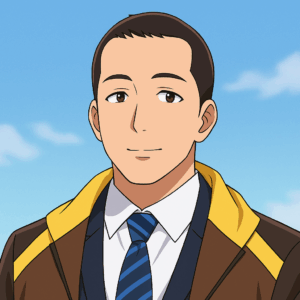自筆証書遺言書作成の注意点
目次
1・ 自筆証書遺言の法的要件(民法968条)
(1)全文を自筆(本人の手書き)で書くこと
- パソコンや代筆、録音・ビデオは無効です。
- ただし、財産目録のみはパソコン可です。(2019年の法改正)
→ ただし各ページに署名・押印が必要になります。
(2)日付を明記
- 「令和○年○月○日」など具体的に記載します。
→ 「○月吉日」「2024年春」などは無効の可能性があります。
(3)署名・押印
- 氏名を手書きし、印鑑(認印でも可)を押します。
- 実印が望ましいですが法的には必須ではありません。
2・内容面の注意点
(1)誰に、何を相続させるかを明確に
- 「長男に土地を」「妻にすべてを」では不明確な場合があります。
- 例:「東京都○区○丁目○番地の土地を長男○○に相続させる」等と具体的に記載することが望ましいです。
(2)遺留分に配慮する
- 法定相続人には最低限の取り分(遺留分)があります。
- たとえば「長男にすべて」は、他の相続人に争われる可能性がありますので、作成する際には遺留分を念頭に入れて作成した方が争いを未然に防ぐことができます。
- 遺留分を無視した遺言書を作成したことにより、争いに発展した場合には行政書士の業務範囲を超えることになりますので、新たに弁護士を探す必要がでてきます。
(3)財産の記載漏れに注意する
・財産の記載漏れに注意します。書かれていない財産は「遺産分割協議」の対象となります。
(4)封印は不要(しても可)
- 封筒に入れて封をしてもいいですが、しなくても有効です。
- 保管時の改ざん防止には封印・保管場所の記録が有効です。
3・法務局での保管制度(おすすめ)
- 2020年より、自筆証書遺言は法務局で保管できるようになりました。
- メリットとして、紛失・改ざんの防止や家庭裁判所の検認が不要となることが挙げられます。
- 申請手数料:3,900円と比較的安価です。
- 本人が法務局に出向いて申請します(本人確認あり)
4・まとめ
実務上のポイントとして、
- 読みやすい字で丁寧に書く(争いの種を減らす)
- 修正がある場合は訂正方法も法的要件に従う
- 予備的遺言もおすすめ
- 例:「長男が先に亡くなっていた場合は、次男に土地を相続させる」
- 定期的に見直し・書き直す(状況が変わるため)
等が挙げられます。
せっかく作成した遺言書が無効になったり、字が汚くて後に争いに発展してしまっては元も子もありません。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査・成年後見業務)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!