相続人調査とは?
目次
1・相続人調査とは?
被相続人が亡くなった際に最初にすべきことのひとつであり、誰が相続人であるかを戸籍で確認することです。
「どうやって調査すればいいの?」といった疑問が生じることと思います。
具体的な作業方法については、相続人の範囲と順位を確認した後、戸籍を取得して読み解くことを繰り返し、必要な戸籍を揃えていくことです。

2・相続人調査の手順
(1)相続人の順位及び範囲を確認
相続人調査を始める際には、被相続人のどの続柄の人が相続人になれるかを把握する必要があります。
これを把握していないと誰の戸籍が必要になるか分かりません。
・下記に相続人となる者について記載していきます。
はじめに重要なポイントとして、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外は、第1順位である子どもが相続人となり、もし子どもが亡くなっている場合は、亡くなった人に一番近い直系卑属が相続人になります。
このように、本来相続人となるはずの人が先に亡くなっていた場合、その者の子どもが代わりに相続することを代襲相続と呼びます。
第1順位である子どもいない場合、第2順位である親が相続人となります。両親とも亡くなっている場合は、亡くなった人に一番近い直系尊属が相続人になります。
第1順位の子ども・第2順位の親がいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続します。
なお、兄弟姉妹における代襲相続は一代限りです。
甥姪が亡くなっていても再代襲は認められないので注意が必要です。
(2)被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得する
相続人の順位及び範囲を確認したら次に行うこととして、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得します。
なぜ出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せる必要があるかというと、相続人第1順位である子どもの有無と人数を確定させなければいけないからです。
戸籍謄本には被相続人の子どもの氏名が記載されています。
戸籍は、転籍・結婚・離婚・改製のたびに新しく作成されますが、除籍した子どもの情報は新しい戸籍に引き継がれないため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て揃えないと、子どもがいるかいないか、何人いるのかが確定できないのです。
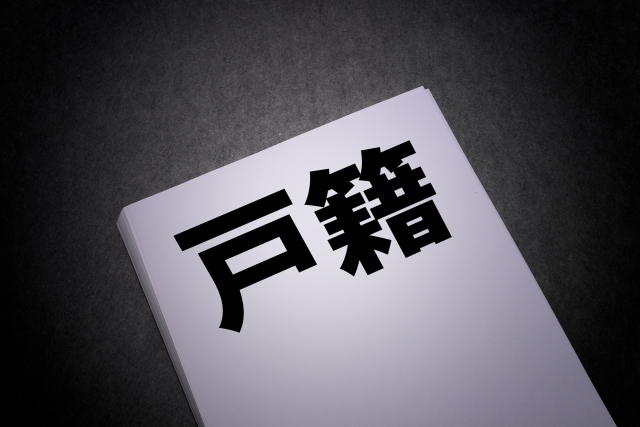
それでは戸籍の取得方法について記載していきます。
相続人調査をする上で、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を死亡時からさかのぼって集めていくのが鉄則です。
手順1・亡くなった人の死亡時の戸籍謄本を取得する
被相続人の本籍地の役所に申請します。
申請方法や手数料、委任状の有無等の詳細は役所によって異なるので、ホームページなどでご確認ください。
申請先の役所において「相続で出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。」と伝えましょう。
そうすれば、その役所にある全ての戸籍謄本を発行してもらえるはずです。
被相続人の最後の本籍地が不明なケースもあると思います。
その場合は、最後の住所地の役所から住民票の除票を取得すれば、本籍地が記載されています。
※間違えて戸籍抄本を取得しないように注意して下さい。
手順2・戸籍謄本を読み解く
読み解くポイントは、下記のとおりです。
(1)ひとつ前(従前)の戸籍謄本の情報を調べる
「戸籍事項」の欄を確認すると、その戸籍が作られた日付と事由が記載されています。
次に亡くなった人の「従前の記録(従前戸籍)」の項目を探してみると、ひとつ前の本籍地が記載されているので、次はその本籍地の役所に、戸籍謄本の発行を申請します。
(2)相続人となる人物を特定する
「身分事項」や「戸籍に記載されている者」の欄で、相続人となる続柄の人物を特定します。
手順3・相続人の戸籍謄本を取得する
亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本を取得した後は、相続人の戸籍謄本を集めていきましょう。
手順2で相続人が確定できる場合もありますが、相続関係が確定できない場合は引き続き戸籍収集が必要です。
いずれにせよ、相続人自身の戸籍謄本も以後の相続手続きで必須になるため、ここで揃えておくと効率がよいでしょう。
(1)必要な相続人の戸籍謄本を確認する
必要な相続人の戸籍謄本は下記の通りです。
| 誰の戸籍謄本を取得するか?の判断材料 | 必要な戸籍謄本 |
| ①常に必要となる戸籍謄本 | 相続人全員分の戸籍謄本 |
| ②先に亡くなっている子どもがおり、代襲者がいる場合 | 亡くなった子どもと代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |
| ③被相続人に存命の子どもと代襲者がいない場合 | ①親の片方が先に亡くなっている場合、亡くなった方の親の死亡が記載されている戸籍謄本 ②(両親とも先に亡くなっており、祖父母で存命な者がいる場合)両親と亡くなった祖父母の戸籍謄本 |
| ④被相続人に存命の子ども及び代襲者と両親(直系尊属)がいない場合 | ①両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ②直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本 ③(被相続人の兄弟姉妹で、先に亡くなっている者がいる場合)亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ④(①~③のうち、代襲者である甥姪で先に亡くなっている者がいる場合)亡くなった甥姪の死亡が記載されている戸籍謄本 |
上の表を見てほとんどの方がこう思うでしょう。
「様々なケースがあり、複雑で難しそう。」「自分でできる自信がない。」
等の感想を抱くことが一般的です。
続けて上記表の右の欄に記載された戸籍謄本を取得していく作業にとりかかります。
(2) 相続人の戸籍謄本を取得する
さて、戸籍謄本が必要な相続人が確認できましたので、相続人の戸籍謄本を取得していく作業に入ります。
大前提として、相続人と連絡が取れるなら、本人やその家族に取得してもらうのが委任状等の書類も必要ないので手間と労力がかかりませせんので協力しながら戸籍収集を進めていきましょう。
相続人と連絡がとれない等、上記の方法での取得が難しい場合は、下記の手順で進めることをおすすめします。
・現在の戸籍謄本・死亡が記載されている戸籍謄本
「被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本」に載っている相続人は取得する必要がありません。
それ以外の相続人については、被相続人の戸籍謄本から、その人の本籍地をたどって現在の分まで取得します。
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本から、その人の本籍地をたどって取得していきます。
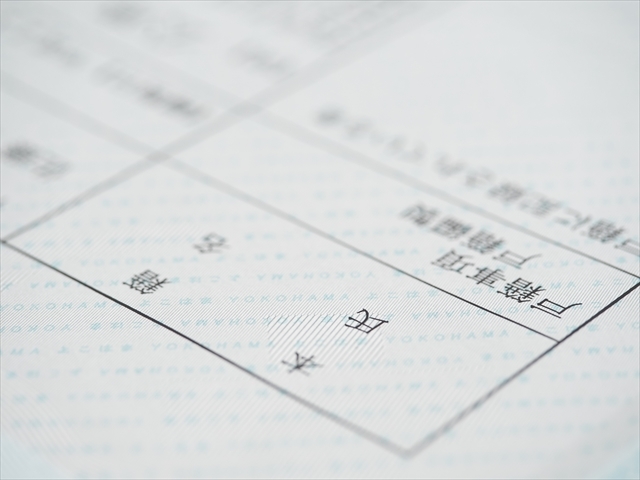
3・相続人調査がなぜ重要なのか?
これまでの記事を読んでいただいた方は
「相続人調査は面倒だ。」「大変そう。」
等といった感想を抱いたことと思います。

しかし、相続人調査は非常に重要な作業であるため、必ず徹底的に行います。
3つの理由を下記に記載します。
(1)遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
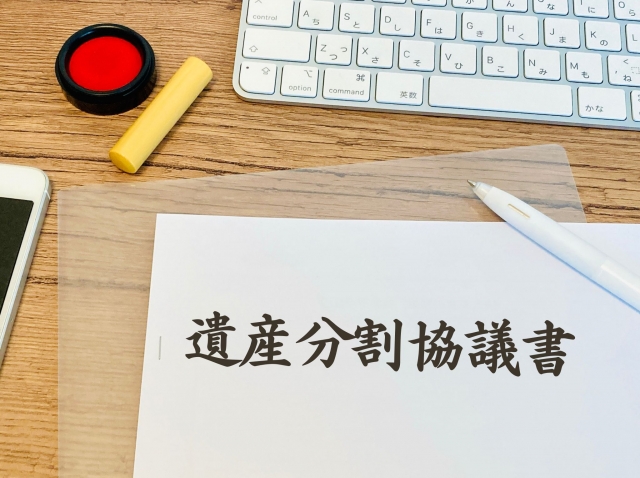
遺言書がなく相続人が複数人いる場合、誰がどの財産を相続するかを話し合う遺産分割協議を必ず行わなければなりません。
遺産分割協議は
・相続人全員で行う必要がある
・1でも欠けていたら無効
・相続人が正式に確定しないと遺産分割協議ができず、その後の相続手続きもできない
等の定めがあるため、早期に相続人調査を済ませる必要があります。
(2)思いもしなかった(想定外)相続人が出てくるかも💦
相続関連業務では、まれに想定外の相続人が発覚することがあるので、その存在の有無を明確にするためにも徹底的に相続人調査を行います。
例を挙げると
養子縁組した子・婚外子・異父母兄弟
などです。
このような想定外の相続人が遺産分割協議の後に発覚した場合には遺産分割協議をやり直さなければなりません。
特に相続財産が多い場合については、トラブルに発展する可能性も高いため、漏れのないようにしましょう。
(3)相続の各種手続きで戸籍の提出を求められる
直近でいうと妻の父が亡くった際の金融機関・年金手続き等、各種手続き際には何処にいっても
「戸籍謄本はありますか?」
と言われました。
相続のあらゆる手続きでは戸籍の提出が必要になるため、相続人調査で必要な戸籍は全て揃えるようにしとくとスムーズに手続きが行えます。
相続人調査で集める戸籍一式は、遺産分割協議書と印鑑証明書とともに、下記のような場面で提出が求められます。
- 金融機関での預貯金の引き出し等の各種手続き
- 不動産の名義変更
- 相続税の申告
等の場面で戸籍謄本が求められます。
提出先の各行政機関にとっては、間違えがあってはならないので「本当にこの人が相続人なのか」「本当にこの人が財産を取得してもいいのか」ということを、厳重に確認する必要があります。
そのために戸籍一式・遺産分割協議書・印鑑証明書が必要になってくるのです。
4・まとめ
これまで相続人調査の手順やその重要性を記載してきましたが、どうでしょう?
ほとんどの方が
「大変そう。」「自分1人では出来ない。」「戸籍謄本を集める時間がない。」
等といったネガティブな感情を抱いたことと思います。
ましてや上記のように長い文章で記載されているのを見るとなおさらです。
しかし、相続手続きにおける最初のステップとして、相続人調査は必ず行う必要があり、ここで躓くわけにはいきません。
当事務所では、相続人調査も対応していますので、是非、お気軽にお問い合せ下さい。
東村山市・清瀬市・東久留米市・所沢市の相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査・成年後見業務)のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお任せ下さい!
もちろん上記以外の地域も対応しております。

